
 ページ内工事中(リニューアル中) ページ内工事中(リニューアル中)
 広報誌「ふれあい」128号 広報誌「ふれあい」128号
 7月は青少年の非行・被害防止全国協調月間です 7月は青少年の非行・被害防止全国協調月間です
 いばらき子どもSNS相談 (茨城県教育委員会)より いばらき子どもSNS相談 (茨城県教育委員会)より
 親子のための相談LINE 親子のための相談LINE
|

「ありがとう」 ……………感謝の気持ち」が育ちます。
「どうぞ」 …………思いやりの心が生まれます。
「おはよう」「こんにちは」…相手との心の距離が近づきます。 |
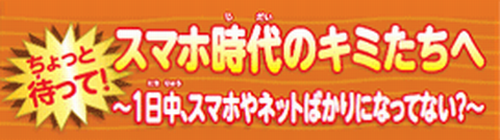 |

 2/18~22 「家庭の日」絵画・ポスター展 2/18~22 「家庭の日」絵画・ポスター展
青少年のための機会を提供して子どもたちがより安全で健康的に成長することを願い、2/18~2/22まで市内小中学校の「家庭の日」絵画・ポスター展を水郷まちかどギャラーで開催。家庭は、ふれあいと安らぎの場であるとともに、青少年の人格が形成される基盤です。また、人との関係のあり方や社会のルールを学ぶ場でもあります。これらのことを家庭や地域が再認識し、「心豊かで明るい家庭」づくりを進めることが望まれています。「家庭の日」をきっかけにして、家庭の大切さや家族のあり方について見つめ直すことを目的に、青少年育成潮来市民会議(潮来市教育委員会)に潮来ライオンズクラブでも継続活動として協賛し市内小中学生の作品6名に潮来ライオンズクラブ賞を贈りました。このような活動が青少年の豊かな人生を送るためのきっかけの一つになればと我々は考えています。「大切なのは、どれだけたくさんのことをしたかではなく、どれだけ心をこめたかです」


 2/10 令和7年度 青少年健全育成茨城県推進大会参加 2/10 令和7年度 青少年健全育成茨城県推進大会参加
次代を担う青少年が、夢と希望を持って 心豊かにたくましく成長し、社会の一員として自立に向かって歩んでいくことは、県民すべての願いです。しかしながら、近年、子どもたちの不登校や引きこもりが増加傾向にあるほか、家庭や地域の教育力の低下、大人の規範意識の低下、情報化社会の進展による人間関係の希薄化など、青少年を取り巻く環境は大きく変化しており、それに伴い様々な問題が生じてきています。このため、青少年を支える大人、とりわけ親が自らの生き方を省み、姿勢を正して、社会の基本的なルールやマナーを、身をもって実践し、よき手本を青少年に示していくことが必要です。そこで、青少年育成関係者と子育て中の親等が一堂に会し、青少年健全育成に向けての思いを新たにするとともに、家庭における親のあり方や地域社会における大人のあり方について考え、家庭、学校、地域社会が相互に連携しながら青少年健全育成活動のさらなる発展を図るため推進大会が開催されました。




 1/18 令和7年度 第4ブロック青少年相談員研修会 1/18 令和7年度 第4ブロック青少年相談員研修会
地域社会での青少年育成活動の積極的な推進を図るため、青少年と一体になり、ともに喜び、ともに語り、青少年のよき相談相手となることを目的に県東地区(鉾田市・鹿嶋市・潮来市・神栖市・行方市)の関係者が年に一度の情報交換等の合同研修会を開催しました。


 1/6 「家庭の日」絵画・ポスター選考会(青少年健全育成活動) 1/6 「家庭の日」絵画・ポスター選考会(青少年健全育成活動)
家庭は、ふれあいと安らぎの場であるとともに、青少年の人格が形成される基盤です。また、人との関係のあり方や社会のルールを学ぶ場でもあります。これらのことを家庭や地域が再認識し、「心豊かで明るい家庭」づくりを進めることが望まれています。「家庭の日」をきっかけにして、家庭の大切さや家族のあり方について見つめ直すことを目的に、青少年育成潮来市民会議(潮来市教育委員会)に潮来ライオンズクラブでも継続活動として後援し市内小中学生の作品6名に潮来ライオンズクラブ賞を贈ります。このような活動が青少年の豊かな人生を送るためのきっかけの一つになればとクラブでは考えています。

 11/28 潮来第二中学校(薬物乱用防止活動) 11/28 潮来第二中学校(薬物乱用防止活動)
潮来市立第二中学校(53名)、地域社会と連携をとり薬物乱用防止教室を開催し冬休みに向けた生徒指導として薬物乱用防止教室を行いました。
また、今後も委員会を中心にに地域社会に溶け込んだ奉仕活動を今まで以上に推進していきたいと考えます。We Serve

 11/15 令和7年度 潮来市青少年のつどい 11/15 令和7年度 潮来市青少年のつどい
「令和7年度 潮来市青少年のつどい」市内の小中学校、高等学校、から選出された、11名の児童・生徒の皆さんが未来に向けて考えていることや、日常生活、学校生活の中で感じていること、大人達に伝えたいことを発表してくれました。
今、子どもたちには、将来、社会的・職業的に自立し、社会の中で自分の役割を果たしながら、自分らしい生き方を実現するための力が求められています。この視点に立って日々の教育活動を展開することこそが、子どもたちの発達の段階にふさわしい社会教育活動、将来を大きく左右する学生時代、子どもたちが後悔しないようにしたい。そのために、意欲的に働ける未来を迎えるため、今後も青少年に発表する機会を提供することにより、現代の青少年に対しする地域社会の理解を深めるとともに、ふるさと「潮来」の未来を担う若い世代の健全育成を図ることを推進していきたいと考えます。また家庭・学校・地域社会において薬物乱用を許さない環境づくりに役立ていただくためにチラシを配布し薬物乱用防止啓発活動もおこないました。


 5/29 令和7年度 青少年育成潮来市民会議総会 5/29 令和7年度 青少年育成潮来市民会議総会


 2/15 市内青少年育成団体 合同研修会 2/15 市内青少年育成団体 合同研修会
鹿行生涯学習センターで開催された、第4回茨城県生涯学習・社会教育交流大会に参加しました。今後の青少年の育成活動に役立てたいと考えます。
 2/11 令和6年度 「家庭の日」絵画・ポスター展 2/11 令和6年度 「家庭の日」絵画・ポスター展
青少年のための機会を提供して子どもたちがより安全で健康的に成長することを願い、2/11~2/16まで市内小中学校の「家庭の日」絵画・ポスター展を水郷まちかどギャラーで開催。家庭は、ふれあいと安らぎの場であるとともに、青少年の人格が形成される基盤です。また、人との関係のあり方や社会のルールを学ぶ場でもあります。これらのことを家庭や地域が再認識し、「心豊かで明るい家庭」づくりを進めることが望まれています。「家庭の日」をきっかけにして、家庭の大切さや家族のあり方について見つめ直すことを目的に「家庭の日」絵画ポスター展を開催しました。

 1/26 第4ブロック(鉾田市・鹿嶋市・潮来市・行方市・神栖市) 1/26 第4ブロック(鉾田市・鹿嶋市・潮来市・行方市・神栖市)
令和6年度 青少年相談員研修会
青少年の健全な成長のための社会環境づくりを進めるためには、関係する業界や青少年育成に関係する団体、行政の協力体制が不可欠です。


 11/28 令和6年度 第2回潮来市学校警察連絡協議会 11/28 令和6年度 第2回潮来市学校警察連絡協議会
(いじめ問題対策協議会)
潮来市内小中高等学校・市内青少年育成団体が冬休みに向けての情報交換や小中高での連絡事項が行われ行方警察署から長期休暇は青少年の非行・被害防止全国協調月間」であり多くの青少年に対する助言をいただきました。

 11/1 あいさつ・マナーアップキャンペーン 11/1 あいさつ・マナーアップキャンペーン
地域社会での人間関係の希薄化、家庭や地域社会の教 育力の低下などから、青少年の様々な課題や問題が生じています。 こうした課題や問題を解決するためには、先ず、地域 の大人と子ども、大人同士、子ども同士のコミュニケー ションを広げることが大切です。 そのきっかけづくりとして、「あいさつ・声かけ運動」を展開しています。 11月は、「いばらき教育月間」に呼応し、「あいさつ・ 声かけ運動」を地域育成団体・教員・保護者の協力で、潮来市立延方小学校・潮来第二中学校・県立潮来高等学校 小中学校では「朝の挨拶」高校では。「さわやかマナーアップ」 服装、あいさつ、マナー」を合言葉に、通学中の生徒へ挨拶指導及び一般市民へも呼びかけました。

 11/2 第二回青少年のための社会環境整備 11/2 第二回青少年のための社会環境整備
次代を担う青少年がたくましく心豊かに成長することは、世の全ての親の願いであるとともに、私たちに課せられた重要な使命です。また、それは社会全体が担うべきものであり、青少年の健全育成に我々一人ひとりがかかわっていくことが重要であるのではと考えます。潮来市内小中高及び各青少年育成機関と協力し有害ビラや有害たて看板を撤去し、青少年に関係が深く青少年の健全育成に向けた取り組みにご協力いただける店舗を、「青少年の健全育成に協力する店」と位置づけ、その登録活動を行いました。困難を有する子供・若者が、速やかに困難な状態から脱し、あるいは困難な状況を軽減・コントロールしつつ成長・活躍していけるよう、家族を含め、誰ひとり取り残さず、かつ非常時においても途切れることなく支援し、子どもの多様な価値観を認め、家族内のコミュニケーションを図るように心掛け、いつでも親や学校、地域社会が温かく見守り、子どもを孤立させないことが大切です。
「いつの時代でも、その時々の社会を支え、子供の躾、教育にあたるのはおとなたちである。青少年は、その時々のおとなによって教え、躾けられて成長し、次の時代を担っていく。だから、子供に対するおとなの責任というものは、いつの時代においてもきわめて重い」

 8/1~8/3 潮来祇園祭礼巡視 8/1~8/3 潮来祇園祭礼巡視
青少年をとりまく環境は年々複雑かつ多様化し、青少年の健全な成長を阻害する幾多の要因を生み出してきています。その結果、非行の増加・低年齢化をはじめとして情緒の安定を欠いたり、対人関係がうまくとれないなど、変化する環境に適応できない子どもたちが目立って増えてきています。夏休み中は、生活のリズムを崩し、心身のバランスも乱れ、本来打ち込むべき学業にも影響を来します。巡視活動は、地道な取組みではありますが、最も重要な活動だと私達は考えます。市内青少年育成団体と潮来高校PTAが祭礼巡視活動を行ないました。

 7/9 令和6年度 第1回潮来市学校警察連絡協議会 7/9 令和6年度 第1回潮来市学校警察連絡協議会
(いじめ問題対策協議会)
市内小中高等学校・市内青少年育成団体が夏休みに向けての情報交換や小中高での連絡事項が行われ行方警察署からは「7月は青少年の非行・被害防止全国協調月間」であり多くの青少年に対する助言をいただきました。潮来ライオンズクラブでは、青少年健全育成委員会が出席して薬物乱用防止三つ折りチラシを配布し啓発活動を行いました。

 7/6 第一回青少年のための社会環境整備 7/6 第一回青少年のための社会環境整備
次代を担う青少年がたくましく心豊かに成長することは、世の全ての親の願いであるとともに、私たちに課せられた重要な使命です。また、それは社会全体が担うべきものであり、青少年の健全育成に我々一人ひとりがかかわっていくことが重要であるのではと考えます。潮来市内小中高及び各青少年育成機関と協力し有害ビラや有害たて看板を撤去し、青少年に関係が深く青少年の健全育成に向けた取り組みにご協力いただける店舗を、「青少年の健全育成に協力する店」と位置づけ、その登録活動を行いました。困難を有する子供・若者が、速やかに困難な状態から脱し、あるいは困難な状況を軽減・コントロールしつつ成長・活躍していけるよう、家族を含め、誰ひとり取り残さず、かつ非常時においても途切れることなく支援し、子どもの多様な価値観を認め、家族内のコミュニケーションを図るように心掛け、いつでも親や学校、地域社会が温かく見守り、子どもを孤立させないことが大切です。
「いつの時代でも、その時々の社会を支え、子供の躾、教育にあたるのはおとなたちである。青少年は、その時々のおとなによって教え、躾けられて成長し、次の時代を担っていく。だから、子供に対するおとなの責任というものは、いつの時代においてもきわめて重い」

|
未来を担う子供たちの豊かな学びや成長を支えるためは、地域と学校がパートナーとして連携・協働することが求めれれています
(文部科学省より)
 |
 .毎年11月1日は「いばらき教育の日」、 .毎年11月1日は「いばらき教育の日」、
11月は「いばらき教育月間」です。
子どもたちの規範意識・社会性の不足、家庭の教育力の低下など、さまざまな教育の問題が指摘される中、学校と家庭、地域社会が連携して社会全体で教育の重要性を再認識する契機とするため、茨城県では毎年11月1日を「いばらき教育の日」、11月を「いばらき教育月間」としています。 |
 毎月、第3日曜日は「家庭の日」です。 毎月、第3日曜日は「家庭の日」です。
家庭は、ふれあいと安らぎの場であるとともに、青少年の人格が形成される基盤です。また、人との関係のあり方や社会のルールを学ぶ場でもあります。これらのことを家庭や地域が再認識し、「心豊かで明るい家庭」づくりを進めることが望まれています。「家庭の日」をきっかけにして、家庭の大切さや家族のあり方について見つめ直してみましょう。お父さん、お母さん子どもたちとふれあう時間を持っていますか?本当は毎日が家庭の日です。忙しい毎日の中では、家族のふれあいが薄れがちですが、「家庭の日」には、家族みんなで話し合いやスポーツをしたり、そろって食事をするなど、楽しい団らんのひとときを過ごしてみませんか |
 なんらかの事情で高等学校をやめてしまったみなさんへ なんらかの事情で高等学校をやめてしまったみなさんへ
もう一度、高校教育をうけてみませんか学校は知識や生きる力を学ばせてくれるところです。もう一度勉強したい,過去の勉強をやり直したいという気持ちはとても大切だと思います。県立がだめでも,私立で受け入れている高校もありますので,今の前向きな気持ちを大切に,少し勇気をだし夢を追ってみませんか。 |
 「お父さん、お母さん!子どもの心が見えますか」 「お父さん、お母さん!子どもの心が見えますか」
- ことば・動作などからのSOSサインにいち早くきづき、対応できるようにしましょう
- 子どもの長所を見いだし、上手にほめましょう
- 機会をとらえ、親子の語らいの時間をもちましょう
- 親が本気で子どもを信頼すれば、子どもは親を尊敬します
- 親はいつでも、子どもの未来に明かりを灯す一言を
その一言で自信をもつ/やる気をもつ
|
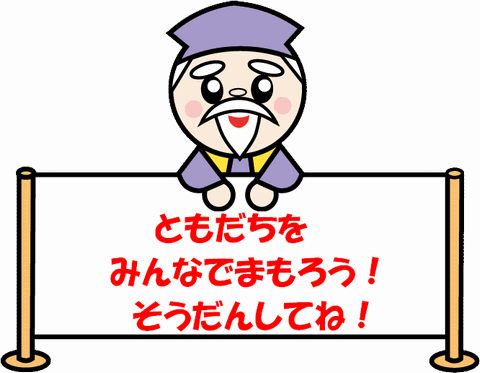 |
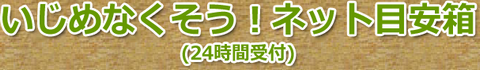 |
笑顔あふれるクラスをつくりたい、ライオンズクエストはそんな先生の願いを叶えます。「ライフスキル教育プログラム」 ライオンズクエストは、エビデンス(学術的に検証され、認められた効果)に基づくプログラムです。青少年が、思いやりと能力を備えた社会の一員となるために必要な、意味ある経験をする機会とあたたかい人間関係を提供し、青少年とその家族を取り巻く世界の変化に対応することをねらいとしています。自律心、責任感、よい意思決定、他者の尊重、そして社会貢献する心を養うスキルや行動を教えることにより、青少年が21世紀における家庭生活、市民生活、そして働くことへの責任を負う準備を手助けします。
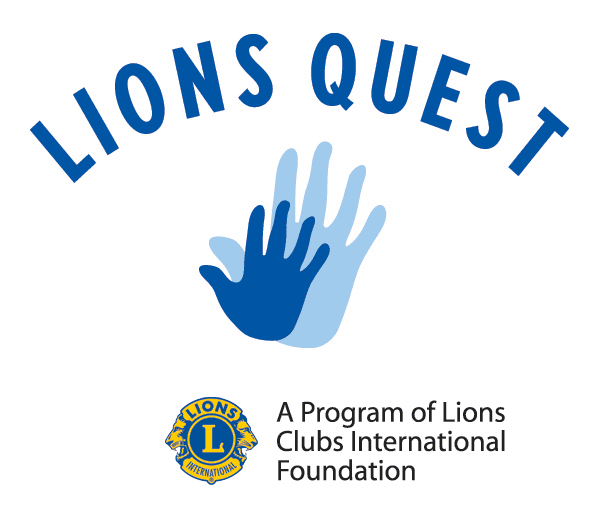
|


